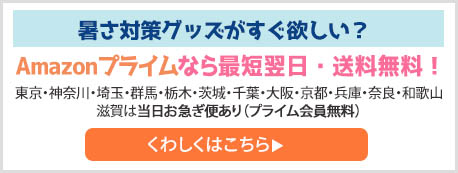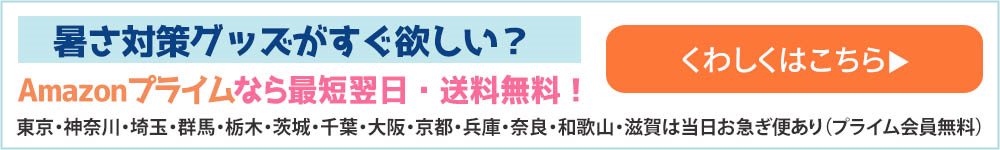気温だけでは判断できない「暑さの危険度」。その指標として注目されているのが「WBGT(暑さ指数)」です。
家庭や職場でWBGT計測器を導入したものの、「数字の意味がよく分からない」「いつ注意すべきか不安」という声も少なくありません。
この記事では、WBGTの数値の見方や使い方を、医療や専門用語に頼らず、どなたでも理解しやすい形で解説します。
WBGT(暑さ指数)ってなに?
WBGTは「Wet Bulb Globe Temperature」の略で、日本語では「湿球黒球温度」と呼ばれます。
気温だけでなく、湿度や日差し(輻射熱)を総合的に考慮して、「人が感じる暑さの負荷」を数値化した指標です。
もともとアメリカ軍が熱中症予防のために開発したもので、現在では日本でも広く使われ、学校、企業、自治体などで暑さ対策の基準として活用されています。
WBGT値の見方と行動の指針
WBGTは温度によって「こんな行動を取るべきだよ!」と教えてくれる数値です。
5段階に分けられていて、各行動の目安は以下となっています。
| WBGT値(℃) | 暑さレベル | 行動の目安(一般的な例) |
|---|---|---|
| 31℃以上 | 危険 | 激しい運動は避け、休憩と水分補給を徹底 |
| 28$301C30.9℃ | 厳重警戒 | 激しい運動は中止、こまめな休憩を |
| 25$301C27.9℃ | 警戒 | 適度な休憩と水分補給を意識 |
| 21$301C24.9℃ | 注意 | 暑さに弱い人は無理をしない |
| $301C20.9℃ | ほぼ安全 | 通常の生活で特に問題なし |
※上記は一般向けの参考指針です。具体的な行動判断は各自の体調・状況に応じて判断してください。
環境庁の「熱中症予防情報サイト」に詳しい情報が掲載されています。
WBGT計測器の見方
WBGT計測器の見方はいたってカンタンです。例えば、タニタの計測器ですと、画像のようにだれでも一目で分かるように作られています。
マークが現れているところがその時点でのWBGT値ですから、水分を取ったり、無理な外出をしないようにしたりと、行動に注意するようにします。
これなら子供でも高齢者でもすぐにわかりますから、家族全員に持っておいてもらいたいです。


WBGTの表示タイプはさまざま
市販のWBGT計測器には、以下のような表示タイプがあります:
- 数値表示型:WBGT値が液晶で表示される
- 色表示型:注意レベルを色で示す(青・黄・赤など)
- アラーム型:設定温度を超えると音で警告する
屋外ではアラーム付きモデル、高齢者や子どもには色で見えるモデルが使いやすい傾向です。
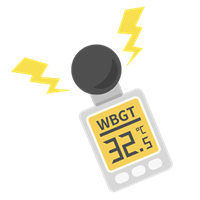
計測する場所もポイントです
正確なWBGTを知るには、直射日光を避けた風通しの良い場所での測定が基本です。
ただし、実際の作業や運動をする場所と同じ環境で測ることで、より実用的な判断ができます。
エアコンの室内と屋外で数値が大きく異なることもあるため、必要に応じて複数の場所をチェックするのが理想です。
WBGT計測器のよくある質問
Q. 「気温30℃」と「WBGT30℃」は違うの?
A. はい、WBGTは気温だけでなく湿度や日射なども加味した指標なので、気温よりも高くなることがあります。
Q. WBGT値が高いときは何をすればいい?
A. 無理な運動を避け、休憩や水分補給、涼しい場所への移動などが大切です。具体的には、環境庁の「観光庁 熱中症予防情報サイト」を参考にして下さい。
Q. 測定器の値が変動するのはなぜ?
A. 人や風、日射、地面の状態などの影響でWBGT値は変動します。こまめな観察を心がけましょう。
WBGT値がわかったら、熱中症対策を万全に
WBGTを正しく測定しても、暑さ対策ができていなければ意味がありません。
以下の記事では、家庭や学校、作業現場で使いやすいWBGT計測器を5つ厳選して紹介しています。