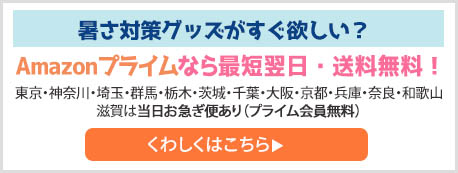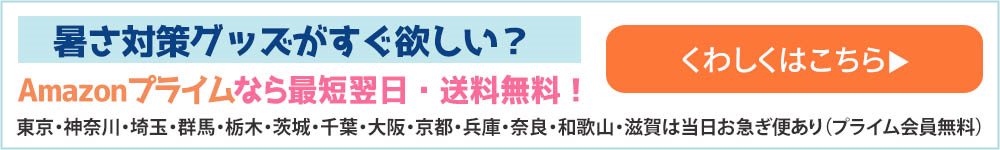地震や真夏に来る台風などの自然災害は、いつも想定外の形でやってきます。そしてその後の停電…
考えたくもないですが、高確率でありえること。
夜中に突然の地震が起き、気がつけばエアコンも扇風機も止まったまま。外は30℃超え、室内は蒸し風呂状態。スマホの充電も気になるし、家族も不安そう――
そんなとき、すぐに使える「電気に頼らない暑さ対策グッズ」があるかないかで、その後の数時間$301C数日間の快適さ、そして安全性が大きく変わってきます。
ここでは、電気が使えない非常時でも、暑さから身を守るために備えておきたいグッズを厳選してご紹介。
実際の災害時の事例や、子ども・高齢者・ペットなど特に注意が必要な人たちのための工夫も交えながら、「いざというとき役に立つ使えるアイテム」をまとめています。
ふだんの生活ではあまり意識しないけれど、「猛暑日に電気が使えない」という状況は、想像以上にきびしく命に関わることもあります。いつ来るか分からない災害に備えて、自分の環境に合った対策を一つでも早く取り入れていただければ幸いです。
電気が止まっても涼しく過ごせる!災害時に役立つ暑さ対策グッズ12選
停電中はエアコンも扇風機も使えず、室内に熱がこもりやすくなります。そんな中で少しでも涼しく快適に過ごすために、「電気がなくても使える」「安全で繰り返し使える」グッズを準備しておくことが重要です。ここでは、災害時に本当に役立つ12の暑さ対策グッズを、用途ごとにご紹介します。
1. 手動・ソーラー式の送風アイテム|風を作る原始的だけど確実な方法
・うちわ・扇子
昔ながらの手動送風アイテムですが、停電時には最高にシンプルで確実。特に大判のうちわは風量も強く、濡れタオルと組み合わせれば冷却効果が倍増します。
Amazonでみる 楽天市場でみる
・ソーラー充電式ハンディファン
晴天時に太陽光で充電できる扇風機。USB充電に対応したタイプならモバイルバッテリーでも使用可能。風の流れを作るだけで体感温度が大きく変わります。
Amazonでみる 楽天市場でみる
2. 清涼感を得る冷感アイテム|汗・体の熱を拭いながら快適に
・大判の体拭き用ウェットシート
シャワーが使えない状況でも全身を拭けてさっぱり。体表の汗や皮脂を拭き取ることで、ムレを防ぎながら体温を効率的に下げる効果があります。避難所生活では特に重要。
Amazonでみる 楽天市場でみる
・ドライシャンプー(スプレー・泡タイプ)
頭皮のベタつきや不快感を軽減し、気分的な暑さを和らげる効果も。断水時にも使えるため、災害時の“清涼感”維持に役立ちます。
Amazonでみる 楽天市場でみる
・冷却シート・瞬間冷却パック
冷蔵庫不要で使える冷却アイテム。おでこや首、脇の下などに貼って一時的に体温を下げるのに効果的。使い捨てですが、備蓄に向いています。
Amazonでみる 楽天市場でみる
・冷感タオル(水少量で繰り返し使用可)
一度水を含ませて軽く振るだけで冷たさが戻る特殊素材。わずかな水で済むため、節水が求められる状況でも使いやすいアイテムです。
Amazonでみる 楽天市場でみる
3. 身につけて涼しい衣類・冷却ベスト
・接触冷感インナー
肌に触れた瞬間に冷たさを感じられる特殊素材のインナー。汗をかくほど放熱効果が高まり、服の中の熱を逃してくれます。
・水冷式クールベスト(保水タイプ)
水を吸収して徐々に蒸発させることで体温を下げるベスト。電気不要で繰り返し使えるため、屋内外問わず活用できます。
4. 夜間の快適性を保つクール寝具
・接触冷感の敷パッド・枕カバー
寝苦しい夜でも、ひんやりとした寝具は体温のこもりを和らげます。電気を使わず、汗をかいても洗えるので衛生的です。
・通気性に優れた寝袋やマット
避難所など通気が悪い場所では、熱がこもらない素材や構造の寝具を選ぶだけで快適性が大きく変わります。
・天然い草のゴザ
国産の天然い草の寝ゴザは
5. 発電・蓄電で乗り切るポータブル電源系
・モバイルバッテリー+USB扇風機
扇風機に使える低電力機器をバッテリーで稼働。長時間使用には容量と出力のバランスが重要です。
・ポータブル電源+折りたたみソーラーパネル
昼間に充電→夜間に使用する形で、小型の扇風機やLED照明にも対応。キャンプ用品としても使えるので“ながら防災”にぴったり。ふだんから用意しておきたいNO1アイテム。
6. 室温を上げないための遮光・断熱グッズ
・遮光アルミシート/断熱カーテン
日差しを遮ることで室内温度の上昇を抑える必須アイテム。窓ガラスに貼るタイプや吊るすタイプがあり、非常時にもすぐ使えます。
・すだれ・遮熱ネット・簡易タープ
とにかく室内に熱を入れないことが大切。直射日光を遮るだけで数度の温度低下が期待できます。風通しを保ちつつ遮る工夫が、暑さ対策には欠かせません。
家庭の備えに!「電気が止まっても使える」グッズを選ぶポイント
停電時の暑さ対策では、「何を持っているか」よりも「使えるかどうか」が重要です。せっかく防災グッズを用意していても、いざというときに充電できなかったり、電源がなかったりして使えないと意味がありません。ここでは、災害時に本当に役立つグッズを選ぶためのポイントを解説します。
1. 電源がいらない、または“ためられる”ものを選ぶ
電気不要=確実に使える
うちわ・冷感タオル・ウェットシートなど、完全に電気を必要としないものは最優先で備えておきたいアイテムです。これらは故障の心配もなく、何度でも使えるのが強みです。
充電式なら“いつでも充電できる手段”をセットで
USB充電式の扇風機やライトは便利ですが、モバイルバッテリーやソーラーパネルとセットで備えておくことが絶対条件です。ソーラー蓄電器があれば昼間に発電→夜に使用が可能になります。
2. 「繰り返し使える」 vs 「使い捨て」:バランスがカギ
繰り返し使えるグッズ(冷感タオル・クールベストなど)は経済的でゴミも出ませんが、使用方法を事前に知っておく必要があります。
逆に使い捨てアイテム(冷却シート・瞬間冷却パック・体拭きシートなど)は、直感的に使えて便利ですが、数に限りがあるため「使うタイミングの見極め」が大切です。
▶ おすすめは「使い捨て3:繰り返し7」の比率で備えること。
3. 家族構成・生活スタイルに合ったグッズを選ぶ
高齢者や乳幼児がいる家庭では、「着脱が簡単」「冷たすぎない」アイテムを優先。
ペットがいる場合は、ペット専用の冷感マット(大理石などが理想)や水分補給グッズも考慮。
狭い住環境では「吊るせる」「折りたためる」など、収納性や設置の手軽さも重要な選定ポイントです。
4. 普段づかいできる=“ながら防災”の視点で
「災害用」としてしまうと使う機会が限られ、気づけば劣化していた…というのはありがちな話です。それよりも、「夏の日常生活でも使えるものを選び、使いながら備える」ことが、防災の基本でもあります。▶ たとえば
USB扇風機はアウトドアやオフィスで
クールベストは庭仕事や外作業に
こういった”ながら使い”できるアイテムこそ、実際の災害時にも迷わず使える頼もしい存在になります。
【状況別】家族構成や住環境で備え方はこう変わる!
停電時の暑さ対策は、家族構成や住まいの状況によって、必要なグッズも優先順位も変わってきます。ここでは、代表的な4つのケースを取り上げ、それぞれに合わせた備え方の工夫を紹介します。
1. 子どもがいる家庭の場合
小さい子供や小学生は、体温調整が未発達で熱中症のリスクが高いと言われています。大人が快適に感じていても、子どもはすでに限界ということも。そのため、「冷たすぎない・肌に優しい・安全性の高い」アイテムを意識しましょう。
備えておきたいアイテム例:
- 冷感素材のタオルやガーゼ(肌にやさしく冷却できる)
- 冷却シート(冷蔵庫不要のもの)
- 子ども用の冷感マット(寝汗対策に)
- ウェットシート(顔・手・背中の汗をやさしく拭ける)
🟦アドバイス:
お昼寝や就寝時は、大人と離れすぎない場所で寝かせて、こまめに汗や顔色の様子をチェックしましょう。
2. 高齢者がいる家庭の場合
高齢者は暑さを感じにくく、体内の水分量も少ないため、気づかないうちに脱水症状や熱中症に陥るリスクがあります。また、肌が乾燥しやすいため、刺激の少ない素材・低刺激の清拭用品を選ぶことが重要です。
備えておきたいアイテム例:
- 大判ウェットシート(全身を無理なく拭ける)
- 軽量のうちわや首掛け扇風機
- 保水型の冷却ベスト(濡らして着るだけ)
- 飲みやすい経口補水液やゼリー飲料
🟦アドバイス:
本人の自覚がない場合も多いため、1$301C2時間おきに声かけ・着替え・休憩の時間を取るよう意識づけをしましょう。
3. ペットと一緒に暮らす家庭の場合
犬・猫などのペットは、人間以上に暑さに弱い生き物です。特に停電中は冷房が止まり、室温の急上昇で命に関わることも。熱を逃がせる場所や涼感を得られる工夫が必要です。
備えておきたいアイテム例:
- アルミボードや冷感マット(床に敷いておける)
- 凍らせたペットボトル+タオルで簡易冷却スペースを作成
- ペット用ウェットシート(熱こもり・汚れ対策)
- 給水器 or 使い捨ての水ボウル(断水時にも安心)
🟦アドバイス:
ケージの位置に直射日光が当たらないようにする/ドアを少し開けて風通しを確保する/屋外避難が必要なら、キャリーバッグの中も冷やせるよう準備をしましょう。
4. マンション or 戸建てなど住環境による違い
マンション高層階:
風通しが悪く、熱がこもりやすい。ベランダでソーラーパネルを使うのは◎だが、夜間の暑さが深刻になりやすい。
戸建て平屋:
開けられる窓が多く、風の通り道を確保しやすい。夜間は「地面に近い場所で寝る」ことで熱中症を防げる。
集合住宅(1階):
日陰が多く温度上昇は穏やかだが、防犯面から“窓を開けっぱなし”が難しいため、ポータブルファンや断熱カーテンの活用を。
🟦アドバイス:
どんな住居でも、「どの窓が一番風が抜けるか」「どの部屋が最も日陰になるか」をふだんからチェックしておくと、停電時に役立ちます。
まとめ|「電気がなくても命を守る」備えを
日本の夏は年々暑さを増し、災害による停電と猛暑が同時に襲ってくるケースも決して珍しくありません。
そんなとき、エアコンや冷蔵庫が使えない状況であっても、「どう涼しく過ごすか」「どう命を守るか」をあらかじめ考えておくことが、私たちの暮らしにとって必要不可欠な備えとなっています。
この記事でご紹介したグッズやライフハックは、どれも特別なものではなく、日常の中に取り入れられるものばかりです。うちわ一つ、冷感タオル一枚でも、命をつなぐ暑さ対策になります。
さらに大切なのは、「どのアイテムを使えば自分や家族が安心して過ごせるか」を普段から知っておくこと。いざというときに慌てず、迷わず、行動できるようにすることが、防災の本当の意味です。
「電気がなくても、なんとかなる」
そんな自信と安心感を持てるよう、今のうちに準備しておきましょう。
※本記事は一般向けの情報提供を目的としたものであり、医療的判断や気象状況に関する最終的な判断は、自治体・気象庁・厚生労働省などの公的機関の情報をご確認ください。
🔌ミニコラム:停電時にやるべきこと|意外と忘れがちな“コンセント”の話
災害による停電時、暑さ対策と同じくらい大切なのが「家電まわりの安全確保」です。特に、ブレーカーやコンセント周りの処置は、停電後の通電火災を防ぐためにとても重要です。
コンセントは抜いておこう
停電直後は家電が停止しますが、電気が復旧したときに一斉に通電が始まると火花や火災の原因になることがあります。次のような家電は必ずプラグを抜いておきましょう。
- ドライヤー・電子レンジなど熱を出す家電
- エアコン・ストーブなど高出力機器
- 電気ポット・炊飯器など水を扱うもの
- 古い延長コード・電源タップ
復旧タイミングは読めないからこそ注意
誰もいない時に電気が復旧し、放置された家電が発熱して火災につながる事例も報告されています。
安全のためにブレーカーを落とすのも◎
停電が長引く場合はブレーカーをオフにすることで、電気復旧時の一斉通電を防げます。復旧後は1つずつ順番にオンにするのが安全です。
| やること | 理由 |
|---|---|
| 使用中の家電のプラグを抜く | 復旧時の通電火災を防ぐ |
| 熱を出す家電は優先して抜く | 火種になりやすいため |
| ブレーカーを落とす(余裕があれば) | 通電管理ができて安全 |
| プラグを戻すときは一つずつ確認 | 過負荷を防止できる |
このような“ほんのひと手間”が、家や命を守る大きな行動につながります。暑さ対策と同時に、通電リスクへの備えも意識しておきましょう。